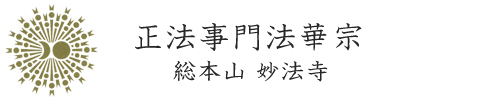私たちは仏教を知っているつもりで、その真髄を知らないのである。仏教を開かれたお釈迦さまについても、なんとなくイメージ的に捉えているだけで、その実像を正しく知っている人はほとんどいないのではないだろうか。
お釈迦さまの母の名はマーヤーといった。彼女はサキャ国の隣国・コーリア国の王女であった。両国は共にサキャ族であり、同じ民族同士の婚姻を重んじる風習があったことから、サキャ国・カピラ城のシュッドーダナ王のもとに嫁いでこられたようである。なかなか子宝に恵まれなかったので、マーヤー王妃には跡継ぎを生まなければならないという負担が重くのしかかっていたにちがいない。
そうして、ようやく果たした懐妊であったが、無情にも産後7日目にして命を落としてしまわれた。生まれた子は「ゴータマ・シッダールタ」と名づけられた。しかし、いのちをかけて産んだ我が子の成長を見ることもなく、マーヤー王妃はこの世を去られたのである。
その母の死がシッダールタの出家に結びついたかどうかはわからない。自分の誕生と引き換えに母が亡くなったという罪悪感のようなものがあったかもしれないし、生と死についての疑問も伏流水のようにながれていたかもしれない。一般に、出家の理由として挙げられている四門出遊※というエピソードは後付けとしても、「いのち」についての疑問から出家されたのはまちがいない。
しかし、さまざまな文献から、出家の最大の原因は人間を殺傷することへの拒否にあったと、私は考えている。古代インドでは、王族は戦闘の神であるインドラ神の再生と見なされていた。敵を殺傷することが神から王族に課せられた義務であった。しかし、シッダールタにとって、人間を創った神が人間に人間を殺傷させるというのは矛盾であった。その不条理を解明するための出家であったように思う。
その頃のインドは戦国時代のような様相を呈していて、250以上あった国々が16カ国に集約されようとしていた。サキャ国は小さな国であったため、いつ滅んでもおかしくない状況にあった。ただ、サキャ族は〝太陽の末裔〟を称するプライドの高い民族であったことから、シュッドーダナ王としては、何としても彼を屈強の王として育て上げたかったにちがいない。
シュッドーダナ王は、愛すべきシッダールタのために、季節ごとにこしらえた宮殿を用意し、たくさんの侍女を侍らせ、武術や学問の侍講も置き、人間の悲惨な光景にふれさせまいと王宮から病人や死人を追い出し、舞踏会を開くなど、あらゆる方法で彼にこの世の楽園を感じさせようとした。また、コーリア国から絶世の美女を花嫁に迎えさせた。それもすべて我が子を出家から引き止めるためであった。かつてシッダールタが生まれたとき、アシタという仙人から「このお方は王になれば天下を制し、出家をすれば悟りをひらくブッダとなられることでしょう」と聞いていた予言が王の脳裏にちらついていたのだろう。
出家だけは絶対に思いとどまらせたいシュッドーダナ王であったが、シッダールタはなかなか心を開こうとせず、引きこもって考え事にふけるばかりであった。しかし、ついに彼は城を捨てて出家してしまう。恵まれた暮らしに満足できず、王族としての規範も承服できない彼にとっての出口は、いのちの謎を解明することしかなかったのだ。彼の出家は後継者である息子ラーフラが2歳くらいのときだったようである。2歳といえばかわいい盛り。そのため仏教を理解していない人のなかには、彼が妻子を捨てた部分のみにフォーカスして、「むごい」、「冷徹」と捉える者もいる。
その頃のインドには、人生を4期に分けて考える四住期という生き方があった。若いときの20年は在家にあって『ヴェーダ聖典』を学習し、その後の約20年は所帯をもって子どもが成人するまで働き、その後は出家して静かな場所で修行し、最後は各地を遊行しながら教え歩く。それこそが人生の理想コースと見なされていた。
シッダールタは8歳のころから、王宮で『ヴェーダ聖典』を侍講から学んだ。そして17歳で後継者のラーフラが生まれたので一応の義務は果たしたことになる。むしろ、ラーフラが生まれるまで出家を延期せざるを得なかったのかもしれない。また、我が子のラーフラという言葉には「邪魔者」という意味があるとされている。本当にシッダールタがそのような意味を込めて名づけたものであるかどうかはわからない。仮にそれが事実であったのなら、息子への愛に溺れてしまう自分自身を恐れていたからではなかったのか。
歴史を見るときに気をつけねばならないことがある。それは現代の感覚で物事の是非を判断しないということだ。時と場合に応じて、対峙する世界を自分の常識では計れないことがある。現代の感覚ならば「お釈迦さまは妻子を捨てた、捨てられた者の悲しみがわからない人間がひらいた悟りなど信じられない」といったところか。しかし、それは現代の常識にすぎない。日頃、家族のために忙しく働く親にとって、子どもを大切に思うのは現代の感覚であって、当時のインドは血縁の情よりも神や信仰を優先する社会だったのである。
その頃のシッダールタはまだ悟りをひらいていないので、家族への愛の正体を「渇愛」と喝破していたはずもないが、少なくとも悟りというものは家族を捨てなければ到底ひらけないものであった。
しかし、城を出て馬を走らせ、ガンジス川を越えたとき、シッダールタは馬引きのチャンナに帰城を命じ、「悟りをひらいたら再会したい。そのときまで元気でいてほしい、と家族につたえてくれ」と依頼している。そこには燃えたぎる決意の一方で、家族を思いやる優しさが感じられる。
人間には「生まれつき」というものがある。自分のことしか考えられない人間は自分のための人生を歩むだろう。家族のことしか考えられないならば家族のための人生、国のために生きる人は国家のための人生を生きる。目的が大きくなればなるほど家族との関わり方が難しいケースは少なくないが、彼の出家も肉親の情を断ち切るものであった。しかし、成道後には父王の帰依、その後は義母も妻も子も弟子になっている。伝承によると、彼らもめでたく悟りをひらいていることから、結果として家族全員が救われたことになる。
それにしても「蝶よ、花よ」と育てられたひ弱な青年が世間をあっと言わせるような行動を起こした。豪奢な生活を捨て、保証すらない悟りの世界をめざした。これは人間の常識をはるかに超えるものである。
先日テレビで、家に引きこもっていた青年が大きな会社をつくるまでのドキュメンタリーが放映されていた。引きこもりの原因はいじめであったらしいが、この青年は暗い部屋にこもりながら、イノベーションによるスタートアップ構想を練っていたという。「世のため、人のために命を懸けたい」と、瞳を輝かせて語る笑顔に、私は人間の無限の可能性を見た。
誰しも若き日の苦悩はある。しかし、その苦悩が世の中を変えるほどの価値創出につながることもないわけではない。生きていくなかで人間はさまざまな困難にぶつかり、思いがけず過ちを犯したり、失敗をしたりすることもある。最近も我が子の犯罪非行に悩む母親に接したが、『煩悩の氷多ければ、菩提の水多し』という言葉を強調するほかになかった。心からめざめることに意味があるのなら、近道、遠回りは関係ない。できることなら失敗や苦悩することなく楽しく生きていきたいが、失敗や苦悩が自分を育て、成長させていく弾みになることだってある。
仏教のすばらしさは、自分の本性を開花させることにある。心に秘められた知恵を具現化することにある。内在無限の可能性をひらくのが真の仏教であり、私たちにとっての悟りなのである。心が人生を決めるというのは誰もが理解しているが、今の仏教は人生をひらく心という視点が弱い。仏教は自分を具現化する教えと捉えられれば、仏教への印象もずいぶん変わっていくはずである。
まど2号(令和5年3月3日発行)

**********************************************************************
季刊誌「まど」は、お釈迦様が残された教えによって、現代を生きる皆さま
の心に一服の癒しを感じていただけるような読み物をめざしています。
電車内やちょっとした待ち時間などに気軽にご愛読ください。
ご購読希望の方は、みずすまし舎までお問い合わせください。
図書出版 みずすまし舎 福岡092-671-9656
「まど」年4回発行(3月・6月・9月・12月)定価150円(送料実費)
☆年間購読のごあんない
「まど」は年間購読をおすすめしています。
お気軽に上記みずすまし舎にお問い合わせください。