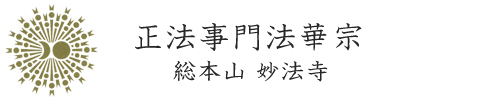かつて、お寺に中門を建設することになったとき、坂道に並んでいた桜たちを切り倒さねばならなくなった。数日後、先代の管長であった父と信徒代表の清水三郎建設委員長が、桜の木を見上げながら何かを話し合っておられた。私が行くと、「来年も必ず咲かせますから、わたしたちを切らないでどこかへ植え替えてください、と桜の木が頼むのだよ」と父が言った。清水委員長は、「こんなに大きい桜の木は植え替えてもたぶん枯れますよ。手間がかかるだけだから、この際、ひと思いに切ってしまいましょう」と勧められたが、父は「咲かすと言ったのだから咲かせてくれるでしょう。クレーンを呼んで植え替えましょう」と決断した。後日、植木屋さんの手で16本の桜が植え替えられた。かれこれ37年前の話であるが、樹齢60年近い桜たちは、今でも春になると参道を桜色に飾ってくれている。
植物の声を聞くと言ったら嗤われることだろうし、植物に感情があるなんて誰も思わないだろう。しかし、「ほめる言葉」をかけ続けた植物はいきいきと生長し、「ののしる言葉」をかけ続けた植物は元気がなくなり、やがて枯れてしまうそうだ。植物の音楽の好みは「ロック」よりも「クラシック」だとか。また、植物はそれぞれ独立して生息しているように見えるが、実は、地中に張り巡らされた菌糸のネットワークなどによって、コミュニケーションを図り、お互いに助け合っている。たとえば、サバンナ地帯のアカシアという木は、キリンなどの草食動物に葉っぱを食べられると、匂いを放出して近くの仲間に危険を知らせるという。ほめられると元気になったり、さまざまなコミュニケーション手段で助け合ったりしながら生きている姿は、植物にも感情や知恵があるという証拠ではないだろうか。
古代インドの時代に、お釈迦さまがそのような植物の生態を詳細にご存じだったとは思えないが、菩提樹の下で観察されたのは「自然智」であった。暑いとき、洪水のとき、菩提樹が生き抜く姿に着眼し、目に見えない根にエネルギーを蓄積したり、根や葉を茂らせる営みを観察された。そこから、人間が苦しみから解放される道を悟られた。
私たちは、外部の情報を目、耳、鼻、舌、身の五官でキャッチし、脳で認識している。そして、自分の思考や感情で処理し、時と場合によっては「乱視交じりの色眼鏡」で受け止めてしまうことも少なくない。仕方がないといえば仕方がないのだが、お釈迦さまはそれを「無明」と呼ばれた。人間の心の奥には自分の都合のいい解釈をしがちな無明がある。しかし、人のために尽くそうという気持ちや、他者の悲しみや苦しみを見捨てられない気持ちもある。それはちょうど薬草が病気を治す効能を発揮するようなものだろう。それをお釈迦さまは「薬性」と呼ばれている。人間には、どうしようもない心と同時に、美しい心も具わっている。
私が言いたいのは、「目に見えるもの」の奥には「目に見えないもの」があるということである。お釈迦さまが真理を悟られたのは、カタチや現象の奥にある本質や真実を読み取る知見力をおもちだったからである。
仏教では禅定によって「涅槃」という境地に入れると教えている。禅の最初は雑念ばかりだが、訓練をつづけるうちに「正見」が得られる。お釈迦さまは禅定修行によって、そのような知見力をもたれたのであった。
「知見」を辞書で引くと、「実際に見て知ること」、「見て知った知識のこと」とあるが、一般的な知見は五官をとおして得るものである。けれども、お釈迦さまは物事の真実を五官で知見されたのではなく、意識で感得された。漁師が投げ網を水面に投げ広げて魚を獲るように、物事の真実や本質をすくい上げられた。心で転がしたり、ふるいにかけたりしながら正しく真実を知り、その上で一人ひとりに慈悲の法を説かれた。病院でいうと、あれこれ検査機器を使って診断し、処方せんを出すようなものである。
間違いや勘違いをしがちなのが人間であるが、それを少なくしていくことはできる。それは物事を少し深く、あるいは先のことを考慮する感覚を身につけることである。「知見」の「見」は観察力のことで、「知」は洞察力を指すといえる。観察力とは人物や物への事実に即した状況把握、いわゆる「目に見えるもの」に気づく能力。洞察力とは「目に見えないもの」を的確に解明することである。先述した桜の話もそうだが、自分が為すべき課題、周囲の気持ちなど、目に見えないものがどこからともなく伝わってくるのである。
この知見力は一種の「霊能力」と呼んでもいいかもしれないが、幽霊や生霊などを感知したり、霊的な力を使ったりするなど、一般におどろおどろしいイメージがあるので、私としてはあまり好きな表現ではない。お釈迦さまは意識の深い部分で真理を読み取られた。しかも、現実世界の奥にある本質存在を把握しながら、目に見える現実を否定することなく、誰もが取り組める普遍的な行法を悟られた。そのように考えると、お釈迦さまの悟りとされている「十二因縁」、「四諦の法」の目的は、知見力による無明の打破といってよい。
むろん、お釈迦さまのような知見の眼をもつことは容易ではない。今やお葬式をすることがお坊さんの主たる仕事と思われ、人びとは「目に見えないもの」について考える暇もないほど現実に追われている。現代に求められているのは判断力、決断力、行動力に富んだ人間である。社会の流れや消費者のニーズを読み取ったり、自分が果たすべき命題のポイントを把握したり、さまざまな変化にうまく対応できる人材が求められている。
著名な経営者であり、禅僧でもあった稲盛和夫氏は、『生き方』(サンマーク出版)という著書の中で、「この世界の、この宇宙のどこかに『叡智の蔵(真理の蔵)』ともいうべき場所があって、私たちは自分たちも気がつかないうちに、その蔵に蓄えられた『知』を、新しい発想やひらめき、あるいは創造力としてそのつど引き出したり、汲み上げたりしているのではないか」と語っておられる。ビジネスモデルの構築から経営に至るまでの知恵のことであろうが、ひたすら無を求める禅僧でありながら、無から有を生じることに言及されている点がおもしろい。たしかに、判断や決断の精度によって、仕事の成果が左右されるのは間違いない。
2500年前、お釈迦さま御在世のインドでは、人間の素晴らしさなど完全に否定されていた。自由とか人権などは完全に蚊帳の外に置かれていた。バラモン教という絶対神による人間支配の信仰が当時の社会の中心にあり、すべての人間は、神の口から、腕から、腿や足から生まれた存在※註として、神の教えに従うべしと命令される時代であった。おそらくお釈迦さまは、人間を差別するカースト制度について、それが神によって定められたものであるのかどうか、ご自分の苦悩を超えて、全人的な苦悩解決のまなじりを上げられたにちがいない。そして、この「妙なる知見」を得られたのであろう。
お釈迦さまは苦行時代を回顧して、「私はこの厳しい修行をもってしても、なお人間を超える妙なる知見に達することができなかった」と語られている。その「妙なる知見」によって、一人めざめた者として、ご自分の悟りを世俗の人びとに説くべきかどうかを考えられるのであるが、そのことは次号で説明することにしよう。
ともあれ仏教の大きな価値のひとつは、「目に見えないもの」についての知見力を身につけさせる行法を確立したことである。私たちが生きている地球の大地の下に菌糸のネットワークがあるように、心にも目に見えないネットワークがある。多くの人に支えられて、自分という存在がある。妻の気持ち、夫の気持ち、子どもの気持ち、親の気持ち、仲間や同僚の気持ち、そして地球の気持ちを、私たちは知らねばならない。自分さえ良ければいいといういびつな思考を捨て、社会のために自分ができることで貢献する。恩を知り、恩に報いる生き方こそが人間に幸福と平和をもたらすのである。こうなると、もはや知見の眼は宗教というより、人類に内在する叡智の母胎というべきであろう。
まど5号(令和5年12月3日発行)

**********************************************************************
季刊誌「まど」は、お釈迦様が残された教えによって、現代を生きる皆さま
の心に一服の癒しを感じていただけるような読み物をめざしています。
電車内やちょっとした待ち時間などに気軽にご愛読ください。
ご購読希望の方は、みずすまし舎までお問い合わせください。
図書出版 みずすまし舎 福岡092-671-9656
「まど」年4回発行(3月・6月・9月・12月)定価150円(送料実費)
☆年間購読のごあんない
「まど」は年間購読をおすすめしています。
お気軽に上記みずすまし舎にお問い合わせください。