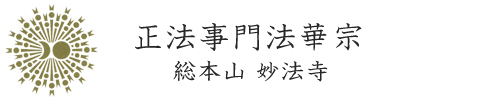真夏のある日、所用のため訪れた京都で、タクシーの運転手さんと話を交わした。
「こんな暑いのに、京都のお寺さんは人が多いね」
「ここはお寺でもっていますからね。でも、多いのは大きな観光寺院ぐらいですよ」
そんな話をしていると、この運転手さん、しだいに愚痴めいたことをこぼし始めた。
「有名なお寺は黙っていても食べられるのでうらやましいかぎりです。こないだ、故郷に帰ると檀家寺で会議がありましてね。お寺では食べられないので、寺の息子さんがお坊さんを辞めるというんですよ。500年の伝統があるので、先代の和尚さん、総代たちに泣いて謝っておられました」
「ほう、500年の伝統があるのに?」
「雨漏りで屋根が腐って改修費が3000万もかかるそうです。寺のがたいが大きい分、費用がかさむ。子どもや孫に苦労をかけたくない、恨まれたくないということでした。同じ宗派の観光寺院が少しカネを回してくれるとありがたいんですがね。桁や梁ひとつ変えるのにも莫大なカネがかかります。歴史とか伝統とか言われても、本人の身になればやってられませんよ」
日本には現在、約7万5千の寺院がある。だが、地方の若者は働き口を都会に求めて故郷を出る。檀家は減る一方だから地方の寺にとっては死活問題なのである。
また信徒側にも不安がある。都会に出た子どもが帰って来なければ、ご先祖様がいつか無縁墓となってしまうかもしれない。何ともさみしい話だが、子どもに迷惑をかけぬよう、自分の代でお墓を閉じる家もあれば、コインロッカーや電車の網棚などに置き去りにされる遺骨も増えているという。
信徒側からすると菩提寺は必要である。葬儀や法事をきちんとしてもらえるならば安心であるが、少子高齢化や過疎化が深刻化している田舎にあって寺院の存続はむずかしい。では、どうすればお寺の存続を図っていけるのだろうか。まず、お寺は変わらなければならない。葬儀・法事という視点だけではなく、基本的に仏教の原点に帰らねばならない。
もともと葬儀・法事は仏教の本来ではない。葬儀は、戦乱や疫病が相次いだ平安時代の末期頃から盛んになっている。そして、江戸時代の徳川幕府がおこなった宗教政策によって、「仏教=葬儀・法事」というイメージが定着してしまった。宗教政策の目的はキリシタンを取り締まることにあったが、過酷な弾圧に苦しむキリシタンと、厳しい年貢の取り立てに苦しむ農民が結びつき、史上空前の一揆を起こした。1637年の秋のことである。
乱の鎮圧後、この事態に衝撃を受けた徳川幕府はすべての民衆をいずれかの仏教宗派に強制的に所属させた。このことをきっかけに檀家制度が確立したのだから、約400年の根強い歴史がある。しかし、信仰心の希薄化、信教の自由、核家族化、少子高齢化、人口の一極集中などによって「家の宗旨」はもはや限界に達している。山は動きつつある。新しい時代が近づいている。「結構な時代になった」と、私は喜んでいる。
私が大学生の頃、「帰属意識」という言葉が流行した。ある集団・組織に所属しているという意識や感覚のことを意味しているのだが、そのころの仏教界は、この帰属意識の根っこが社会の末端まで細かく張り巡らされていて、別の信仰をすると、宗旨の掟を破った者として村八分のような状態になることがあった。そんなせめぎ合いから起こる悩みをしばしば打ち明けられた記憶が私にもある。檀家制度というのは、先祖への忖度、宗派への忠誠心という帰属意識だったのである。私は、そのような閉鎖性を嫌ったが、最近はそんな現象もなくなり、個の自由が観念の縛りを解放していることに喜んでいる。
釈迦仏教は人間の「うずき」や「痛み」を感じ取り、心を治癒する慈悲と知恵に源流がある。檀家制度が敷かれる前の日本仏教にもその理念があって、薬草を提供したり、孤児を引き取って世話をするなど済世利民の役割を担っていた。今の時代、お寺に求められているのは、現代の苦悩に寄り添うことである。
日本のほとんどの寺院にはすがすがしい空間がある。静かな境内の石畳の横には四季折々の木々があり、どこからともなく漂う香の匂いはスピリチュアルな清らかさや落ち着きを与えてくれる。その本堂の奥に在す仏像には、参詣者を包み込む神聖な息吹のようなものがある。あくまで形式にすぎないが、それを利用して檀家を超えて地域の人々に寺を開放するのはいかがであろうか。
ここで問題になるのは、寺が自宗の教義を広めようとする行為である。たしかに、教義は宗教の魂魄であるが、一般人は自分の心が救われ、自分を取りもどすことができればいいのである。釈尊の教えは「応病与薬」といわれている。つまり、釈尊は人間性の原点としてのノスタルジー(故郷や遠い過去を懐かしむ感情)を大切にされた。言うなれば、仏教は本来、人間を安らぎの世界へ帰郷させるものであったのである。
日本の仏教には、檀家制度が敷かれるずっと以前の鎌倉時代、末法思想の台頭によって、それまでの貴族仏教が民衆仏教へ変革された経緯がある。法然、栄西、親鸞、道元、日蓮などは、市井の人々の苦しみを放置できず、母山と呼ばれていた比叡山の峰を下り、それぞれが信じる経典選択に立って新しい宗派を起こした。
反旗のように見えるが、彼らはそれを比叡山延暦寺を建立した天台宗の祖師である伝教大師・最澄への報恩行と考えていた。伝教大師も学問仏教の奈良仏教を否定した。かつての釈尊もバラモン教という既成宗教を破って民衆のための仏教を興した。時代や民衆から乖離した宗教に意味はないからである。よって檀家制度の崩壊は新たな先駆者を育てる機縁というべきである。祖師たちも彼岸からきっと喜んでいることだろう。
「仏教=葬儀・法事」というイメージは、他の仏教諸国、例えば中国や韓国にはあまり見られない。葬儀や法事をしないわけではないが、少なくとも僧侶の仕事の中心ではない。南方の仏教国であるタイやスリランカでは、もっぱら読経や瞑想の場として機能している。各国を回ってみた経験から、葬儀や法事に特化した日本仏教は変容したというしかない。
数年前、仕事で韓国のお寺を訪問したとき、クリスタルでつくられたきれいなお位牌を見ていると、案内係のお坊さんがやって来て「アニエヨ、アニエヨ(違います)」と言って、人差し指で天をさした。
「ニルヴァーナ(涅槃)!」
つまり「あなたはお坊さんなのだから、お位牌などに興味をもたず、天に帰らねばならないでしょ」ということらしい。その後、案内された本堂では、老若男女たくさんの人が瞑想をしていた。韓国には檀家制度がなく参詣も自由なのだとか。別の部屋では僧侶が数人の人生相談にのっていて、その活気ぶりに日本仏教との違いを痛感した。
こんなことを言っても、読者のみなさんにはお寺のことはあまりピンと来ないかもしれない。しかし、寺院の数はコンビニよりも多いのだから、近くのお寺が気軽に利用できたり、お坊さんと親しく話ができたり、地域に開放されるならば、心癒やされる場所や機会が身近なものとなり、現代人の悩みや苦しみも少しは軽くなるのではないだろうか。
私は寺院が心の寄る辺となるよう、旧来の陋習は改革されねばならないと思っている。そのためにも、今こそ釈迦仏教の源流を求める必要があると考えている。そこで、これからしばらくの間、仏教の原風景を紹介した上で、人生や社会についての仏教的な思考を展開することにしたい。
この季刊誌『まど』は、新しい風を取り入れることを理念としている。お寺にもみなさんにも新しい風が吹いてほしいと思うからである。
まど創刊号(令和4年12月3日発行)

**********************************************************************
雑誌「まど」が装いも新たに創刊いたしました。
この「まど」は、お釈迦様が残された教えによって、現代を生きる皆さま
の心に一服の癒しを感じていただけるような読み物をめざしています。
電車内やちょっとした待ち時間などに気軽にご愛読ください。
ご購読希望の方は、みずすまし舎までお問い合わせください。
図書出版 みずすまし舎 福岡092-671-9656
「まど」年4回発行(3月・6月・9月・12月)定価150円(送料実費)
☆年間購読のごあんない
「まど」は年間購読をおすすめしています。
お気軽に上記みずすまし舎にお問い合わせください。