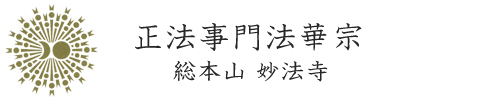電話機を発明したのはベル、電球を発明したのはエジソンだが、彼らが最初にそのことを語った相手は研究仲間だったという。自分が苦心して生み出したものを最初に誰に説明すべきか。これはもっとも神経を使うところである。
経典の伝えるところによると、お釈迦さまが最初に誰に説こうかと思案されたとき、かつて師事した二人の仙人のことが頭に浮かんだという。真理に至る瞑想の境地について、いろいろと指導してくれた二人にまず伝えることが人の道と考えられたのであろう。ところが、二人ともすでに亡くなっていることが心に伝わってきた。そこで、次に自分の身の回りを世話してくれた5人の比丘(修行者)に説こうと考えられた。すでに自分のもとを去っていた5人であったが、喜んでもらいたい一心であったのだろう。「今、どこで、何をしているのだろう?」と思うと、ベナレスにいる5人の様子が心に映ってきたという。
ベナレスはガヤ(お悟りを開かれた場所)から西へ二百数十キロほど離れた場所にある。現在でいうなら、鈍行列車で5時間、歩けば10日はかかる。そんな遠い場所まで、お釈迦さまは焼けつく大地を裸足で歩んで行かれたのであった。「ぜひ、自分の悟りについて説きたい」という強い願いがあったのだろう。
5人は、自分たちに向かって歩んでくるお釈迦さまの姿を遠目に見て驚いた。
「向こうから来るのはシッダールタ(お釈迦さまの名前)ではないか、苦行を捨てて村娘の差し出した乳粥を食べて堕落した男がこんな所までやって来たのは寂しくなったからではないか。話しかけられても絶対に相手にするな」
彼らはシッダールタの成道(悟りを開くこと)を信じて6年間も仕えた結果、期待を裏切られて決別したのである。ところが、いざお釈迦さまが近づかれると、全身にみなぎるようなお釈迦さまの輝きに、足桶をもってきたり、木陰に座をつくったりした。そして、彼らはお釈迦さまの説法を傾聴することになった。
「私はついに仏となった。真理への道には精神の集中が必要であった。疲労と衰弱ではそれができなかった。苦行を捨ててよかった。私はついに悟りを開いたのだ」
そして、そこで説かれたのは「縁起の法」であったと、伝えられている。縁起とは、縁があって起こるということである。物事は単独で存在しているのではなく、無数の要素が互いに絡み合いながら成立していて、モノであれ、肉体であれ、何らかの原因(因)と条件(縁)が合わさって存在している。
仏教界では、この縁起の法について説かれたことを布教の第一歩としている。それに異論を挟むつもりはないが、5人に対してお釈迦さまがそのような理論的な話をされたという点には少し違和感をもっている。経典は仏滅後200年ほどが過ぎてからつくられたものであることから、教法を文字化するときに論理的、定型的にまとめられたと考えるほうが自然ではないだろうか。
お釈迦さまは、まず5人へ6年の間、支えてくれたことに対しての感謝を述べられたことであろう。生老病死の苦を超えようと苦行を言い出したのはお釈迦さまであり、それを放棄すると言い出したのもお釈迦さまであった。彼らに罪はない。ましてや、縁起の法とは、何事も単独で存在するものはなく多くの力に支えられて存在しているという意味である。よって、お釈迦さまは彼らに感謝と謝罪の気持ちを伝え、その後に苦行を捨てた理由を明かし、自分が得た悟りの内容を丁寧に説明されたにちがいない。その話を聞いて彼らは感動し、仏としての人格を感じることで、期待を裏切られたと思い違いをした前非を悔い、弟子になりたいと願い出ることになる。そして、その願いを受け入れられたことで初期教団が発生した、というのが私の見解である。
こうして、ふたたび共同生活がはじまった。まず修行と生活のルールが取り決められ、求道者の集団としての「サンガ」が形成された。最初につくられたルールは不殺生戒・不偸盗戒・不邪淫戒・不妄語戒・不飲酒戒の「五戒」であった。日課としては3人が托鉢に出ると、残りの3人は瞑想や法に関する対話をおこなうというものであった。
一般に、お釈迦さまには自分が指導者という意識はなかったとされているが、悟りを開かれたのはお釈迦さま一人しかおられなかったのだから、瞑想や法に関してお釈迦さまの指導がなかったというのは考えにくい。指導方法は、お釈迦さまからすると「伝法」、5人からすると「聞法」で、これは仏の教えによって自我を溶かす、つまり、仏の生命との融合であった。そして、「涅槃寂静」を教えられた。これは静かに自分の心を見つめ、自我の縛りから解き放たれることに目的がある。お釈迦さまはこの涅槃寂静によって真如の世界を悟られた。
こうして5人の中の阿若憍陳如という者が最初に阿羅漢という悟りに到達し、その後に他の4人も阿羅漢になったと、経典は伝えている。原始仏教聖典の『相応部経典』の中には、阿羅漢果というレベルに達すると「神足通」、「他心通」、「宿命通」などの六神通をそなえることが記されている。きっと彼ら5人はお釈迦さまのような高次な認識力を身につけることを求めたにちがいない。けれども、それは悟りの過程で身につくものであって、それが修行の目的であったわけではない。
では、仏教開教の目的は何であったのか。それは先述するように、人々に自我の観念、つまり欲望や執着からの解放をうながし、安心立命の境地に導くことにあった。苦しみは心に生じるものであり、心はとかく外部で起きる事柄に翻弄されがちだ。死後も意識はあるというのに人々は生に執着し、死後の世界や来世を決める最大要因が心にあることを知らない。そのような人の世をお釈迦さまは「すべては燃えている。目も耳も鼻も舌も身も意も燃えている。すべて、その対象にむかって熾然として燃えている」と述べられた。燃えているのは煩悩の火、生老病死などによる苦悩の火である。この一節から、人々を燃え盛る火から救出して心を安定させ、知見の眼を与えようとされたのがお釈迦さまの考えであったと理解されるのである。
「我思う、故に我在り」とはデカルトの言葉である。考えている自分が自分の存在であるという意味であるが、お釈迦さまの悟りはもっと深く、私たち人間各自の思考や感情のパターンが不幸や幸福につながっていることを喝破された。外部の情報を五官で知覚することで、それが思考にかかり感情へと変化する。苦しみはそこに起こるのであるが、もし、自分を知り、人を知り、世の中を正しく知ることができれば、つまらないことで心を苦しめる必要はない。そこで、お釈迦さまはご自分の悟りを5人に伝え、涅槃寂静を教えることで苦しみを滅し、心を清浄で安楽な世界に導こうとされた。
現在の仏教界では「お題目を唱えよ」、「念仏を称えよ」、あるいは「坐禅を組みなさい」と宗派はそれぞれの教えを説くけれども、残念ながら涅槃寂静に導く教えはあまり説かれていない。そして、お釈迦さまは彼らに「教」を説かれたのではなく、「法」を説かれたのである。教は知識にとどまり、法は心を育てる。お釈迦さまの教えは、あたかも虚空の生命が草木のいのちを伸ばそうとするような慈悲の教えであった。彼らは雨や光を受け止めるように、無心に仏の慈悲と智慧を自分の心に取り入れたのであった。
とにかく、こうしてサンガの門を叩く者が増えていき、やがて双璧となる舎利弗と目連が入門してくる。そのきっかけは、二人が街で話をしているときに見かけた、5人の比丘の一人であった阿説示に、落ち着いた気品と威厳を感じたからであったという。仏教は肉体に真理の命を吹き込むのである。心の王国をつくるという意味で、欧米の仏教学者はこの布教の第一歩を「真理の王国の建設」と名づけている。
まど7号(令和6年6月3日発行)

**********************************************************************
季刊誌「まど」は、お釈迦様が残された教えによって、現代を生きる皆さま
の心に一服の癒しを感じていただけるような読み物をめざしています。
電車内やちょっとした待ち時間などに気軽にご愛読ください。
ご購読希望の方は、みずすまし舎までお問い合わせください。
図書出版 みずすまし舎 福岡092-671-9656
「まど」年4回発行(3月・6月・9月・12月)定価150円(送料実費)
☆年間購読のごあんない
「まど」は年間購読をおすすめしています。
お気軽に上記みずすまし舎にお問い合わせください。